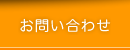開発秘話3:牛タン串
焼き鳥串と同価格を目指して
「価格が高い。調理に技術が必要なのでは?」
牛タンと聞いて生まれる、こうした一般的なイメージ。
それを覆すのが、アトラスプランニングが提供する牛タン串である。
低価格かつ調理に手間がかからない。そんな牛タンをどのようにして実現したのだろうか?
―― 「牛タン串」とは、珍しいですね。
これはまだ流通をはじめていない(2010年8月現在)ものなので、
【リリース予定】としておいていただきたいのですが、
いずれ居酒屋チェーンなどのメニューとして並ぶものです。
牛タンの串、あったら食べたい、と思いませんか?
―― そうですね。でも牛タンと言えば少し値が張る印象もあります。
その通りです。
なぜ高いのかを考えると、
牛タンはご存知の通り牛の舌ですので、供給できる量にそもそも制約があります。
しかも、全体を覆う表皮が硬い。だから調理に手間がかり、価格に反映されてしまうんです。
このように値段が張る条件が揃っているのですが、
ではこれをどうやったら安くできるか、それを考えました。
―― 人的コストと供給量の制約、食品業界全体の課題でもありますね。
そうなんです。
それだけに、正攻法ではコスト削減は成し得ません。
まず、かかる手間について。
硬い、と申し上げましたが、それがこの皮の部分。
もしこの硬い皮を剥かないで調理できれば、大きく作業負担を軽減できます。
そこで、 皮をむかないで調理するには、どうしたらいいかを考えました。
結論としては、やわらかい子牛しかないということになりました。
それも、まだ草を食み出す前、乳を飲んでいる子牛で。
早速そういう子牛が流通しているのか、専門の商社に聞いたのですが、
残念ながら分かりませんでした。
しかし、よくよく考えてみれば、牛乳というものがあります。
文字通り、牛の乳ですから、これはメスから供給されるものです。
こうなると、乳牛の世界では、オスは重用されていないことになります。
調べて見るとこの予感は的中し、
オスの牛は、まだ乳を飲んでいる間に、どんどん処理されているということでした。
処理されたオスの子牛は、
主にフォン・ド・ヴォー(※子牛からとるダシ。フランス料理に使われる)になっているとのこと。
この供給量を聞くと、
当社の顧客チェーンに供給するために足る量であることが分かり、
早速仕入れて開発にあたることにしました。
やはり素材が柔らかいので、調理にかかる手間が軽減できます。
さらに、串刺しにするためにカットする手間を省きました。
それというのは、カットではなく、スライスで薄くしたのです。
それを縫うようにして串に刺すので、
人の手がかかるのはここだけにすることに成功しました。
―― 人的コストと供給量の制約、どちらも解決していますね。
できるコスト削減は、徹底的にやります。
目標は、焼き鳥と同価格にすることです。
そうすれば、誰でも一本くらい食べようかな、という気になると思いませんか?
このケースは、 原料から商品化へとアプローチし、その上でコストの調節を成し得たものです。
しかし、特殊な例というわけでもありません。
それこそ、マグロのトロなんて、戦前までは捨てられていましたものね。
そうしたものの中に潜在する価値を見出すのです。
それに、マーケットは海みたいなものですから、
中には必ず、開発した商品を拾ってくれるお客さんはいるはずなんです。
この両者を探す。
それがつまり、マッチングなのです。