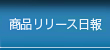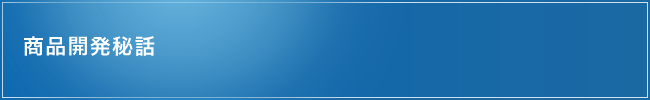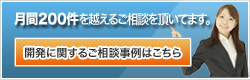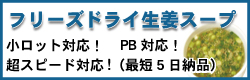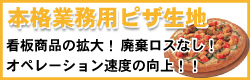アトラスプランニングのモットー
フードサービス、商品企画開発の「黒子役」として
フードサービス業界に向けた商品提案を主として、平成5年3月に創業したアトラスプランニング。
設立以来、業界の黒子的な存在に徹してきたという。
代表取締役である土居内隆弘が、自社の業務内容について語った。
そもそも、外食産業に関わり出したきっかけは何か?
大学在学中(中央大学理工学部物理学科卒)に、
友人の父親が台湾料理居酒屋チェーンを経営しており、アルバイトで手伝うようになったことが直接のきっかけです。
ここの本部で、人や物のマネジメントに携わり、当時の外食産業が抱える問題に直面しました。
その問題とは?
第一に、食材の原価率が不安定であったこと、
第二に、客数が伸びても厨房での人件費が増え、結果的に利益を圧迫してしまうことでした。
在庫が1個、2個と数えられるものが少なく、〜キロという単位で測られるものが多いため、
客数と消費量が連動せずに不安定となり、また仕込みに膨大な人手がかかってしまう。
そこで、同時に解決させるためには
加工度を上げた半製品を店舗に入荷させることが、原価率の安定につながる。
このことを入社半年で思い立ったのです。
加工度を上げたものを使用していれば、アルバイトなど人件費のかからない人員を用いて高品質の料理を提供することが可能。
加工度を上げたものを店舗に仕入れれば、原価も安定する。
当時はファミリーレストランでしか取り入れられていなかった、「セントラル・キッチン」方式を独自に開発して導入しました。
原価率を下げるために、仕入商品だった点心などのメニューをどうにかして内省化できないか、
閉店したラーメン屋の空き店舗を活用して、ここで調理人が朝から晩までひたすら点心作りをして、
できあがったものを物流するというサービスを始めました。
これが当社のはじめの一歩、事業母体ともいえるものです。
このサービスを進めながら、次々と同業他社チェーンに販路を拡大し、会社として興しました。
それが平成5年の3月
22歳のとき、まだ大学在学中でした。
原価率の安定化をもたらすこのアイデアを軸に、
「セントラル・キッチン」という、店舗とメーカーの間における受発注の一元管理システムへと発展させました。
この当時はまだ誰もやっていませんでしたが、今となってはチェーン飲食店の主流となっていますね。
しかしその後すぐに、規模が拡大し、製造工場として進むべきか専門メーカー様に製造委託をするかの岐路に立ちました。
結論は「製造委託」。
創業当時は、そもそも当社が「受託加工メーカー」としての位置付けなのに、
さらに外部企業に「製造委託」をお願いすることに抵抗がありましたが、専門メーカー様は一流の製造設備を持ち、
一方当社は、本物の中華点心(一級点心師)の製造ノウハウを持っている。
両者の強みを掛け合わせれば、新たに「競争のない市場」が創造できるかもしれない…
外食チェーン店でも加工品の需要が高まってきた、まさにその時に合わせたかのように
市場にリリースすることができたわけです。
その後、当社が手掛ける企画商品が増えるのと同時に、パートナー企業様も増え、
パートナー企業様の成功によって、当社の業績を伸ばして頂く、
私どもはあくまで、フードサービス業界の「黒子」的な存在だと自負しています。